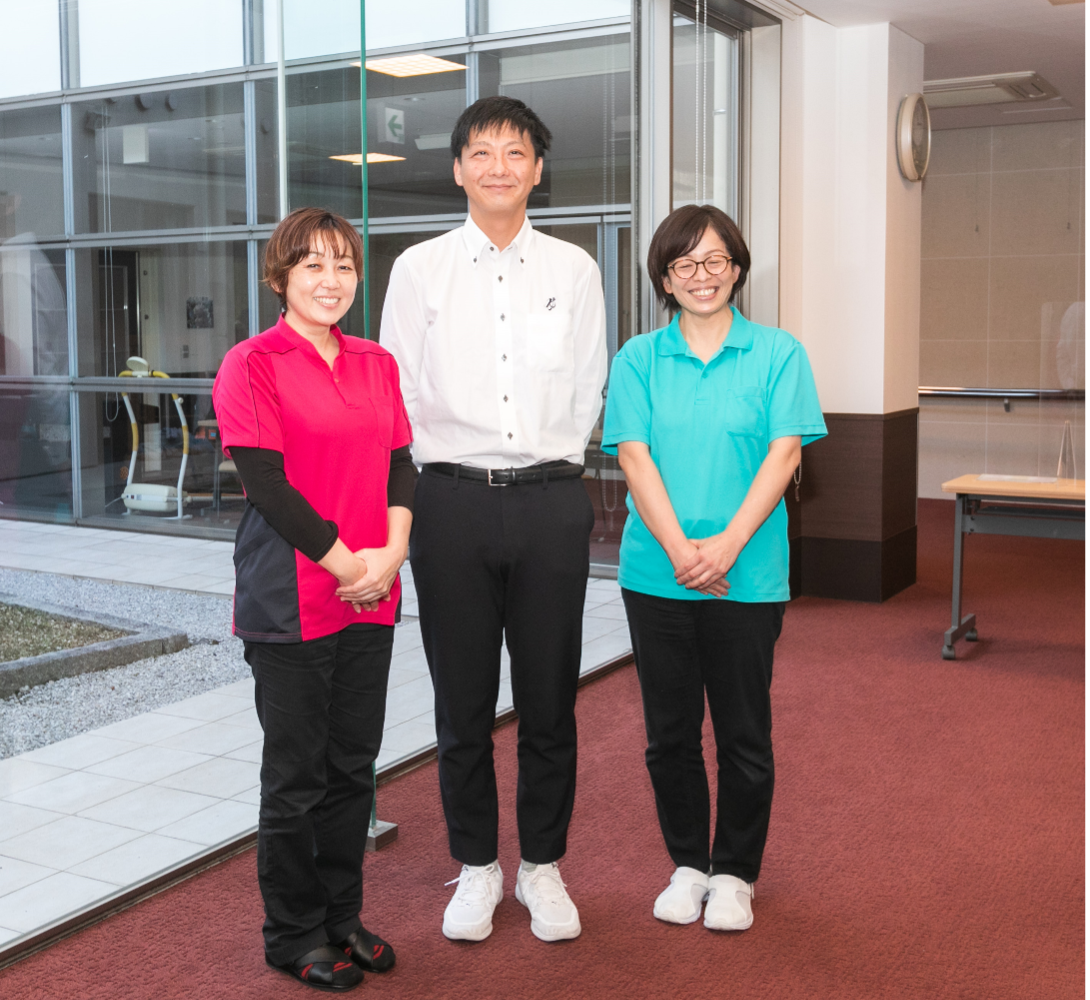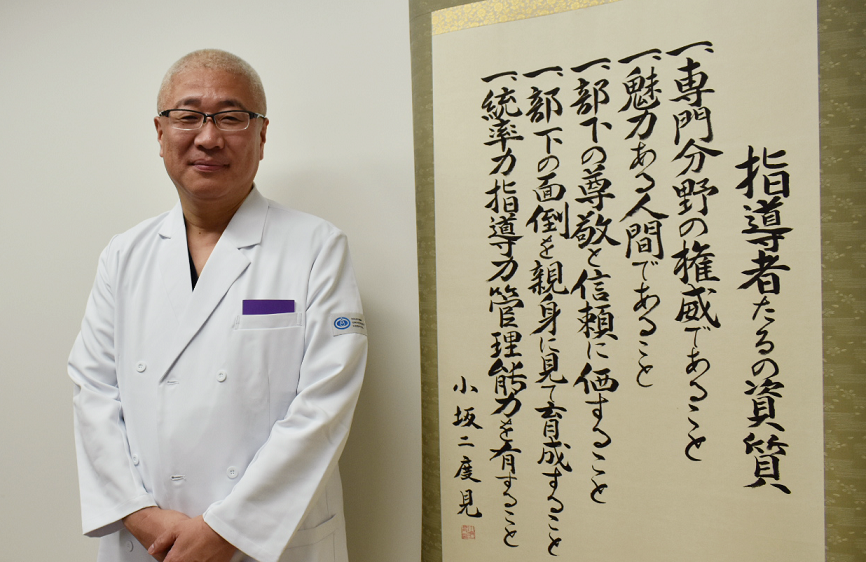
近年、ICUにおいて重症患者の救命率が大幅に高まっている一方で、PICS(集中治療後症候群)などの新たな問題も顕在化しています。集中治療を施すために特殊な環境になりがちなICUを、より患者さんが過ごしやすい環境に近付けるためには、どのような工夫が必要なのでしょうか。岡山大学病院麻酔科蘇生科長であり、集中治療領域の現場経験も豊富な森松博史先生にお話を伺いました。
【プロフィール】
森松博史(もりまつ・ひろし)
岡山大学病院麻酔科蘇生科長、集中治療部長、周術期管理センター長
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学分野教授
1993年、岡山大学医学部卒業。岡山大学医学部附属病院麻酔科蘇生科に入局後、米国留学を経て2003年より同院集中治療部医員に。岡山大学医学部・歯学部附属病院集中治療部助教、岡山大学病院麻酔部講師、周術期管理センター講師とキャリアを進め、2013年より現職。
わずか数日間の入室で昼夜の区別が付かなくなる
――長年にわたり集中治療に携わってこられた森松先生ですが、現在のICUのあり方には疑問もあると伺いました。具体的には、どのようなことでしょうか。
ICUには緊急的・集中的な医学的対応を要する患者さんが入室するわけですが、その環境が患者さんにとってどういうものなのか、これまで顧みられることはあまりありませんでした。どうしても医療従事者の動きやすさや安全性というところが注目されがちだったのです。しかし、昼夜を問わず煌々と明かりが点いていたり、各種機器から大音量のアラームが鳴り響いていたり、スタッフがバタバタと動き回っていたり……、こうした環境は患者さんにとって極めて「異常な環境」だといえます。
この問題について考えるとき、ある先輩医師のことが頭に浮かびます。その先輩は薬物治療の副作用の影響でICUに5日間ほど入室したのですが、退院後にお会いして話を聞いたら、「看護師に『今は8時ですよ』と言われても、朝と夜のどちらなのか全然分からなかった」と言うので驚きました。彼はとても頭脳明晰な人物ですし、入院当時の症状はそこまで重症ではなかった。にもかかわらず、わずか数日間のICU入室で昼夜の区別が付かなくなったというのです。これまでわれわれがICUで提供してきた医療サービスは、本当の意味で患者さんに寄り添ったものになっていただろうか……。そうしたことを考えるきっかけとなった出来事でした。
――昼夜の区別が付かないような環境は、患者さんの心身に少なからず良くない影響を及ぼすのですね。
近年、ICUの領域で注目されているのが集中治療後症候群(post-intensive care syndrome:PICS)という概念です。2012年の米国集中治療医学会で提唱された、ICUの在室中/退院後に生じる運動機能や認知機能の障害などを総称したものです。ICUの環境や、そこで受けた医療行為やストレスなどが原因で発症し、長期的に患者さんの予後に影響を与えるとされています。
例えば、睡眠について考えてみましょう。ICUにいる患者さんは、置かれた環境の特殊性もあって昼間に断続的な浅い睡眠を取ってしまいやすい、あるいはそうせざるを得ないため、夜間の睡眠が十分でなくなるケースが少なくありません。睡眠のパターンが乱れている上にノンレム睡眠の深度も浅く、いわゆる「眠りの質」が低下しているわけです。また、夜間によく眠れなくなるとせん妄の発症リスクが高まり、それがきっかけで投与する薬剤が増えるという問題にもつながっていきます。患者さんのストレスを緩和してPICSを予防するために、ICUの環境面の改善も欠かせません。
なお、現状ではICUで患者さんの睡眠状態を精確にモニタリングすることは難しいといえます。できるだけ患者さんの負担にならないかたちで、ある程度簡便に睡眠状態を測定できるツールが望まれているのです。
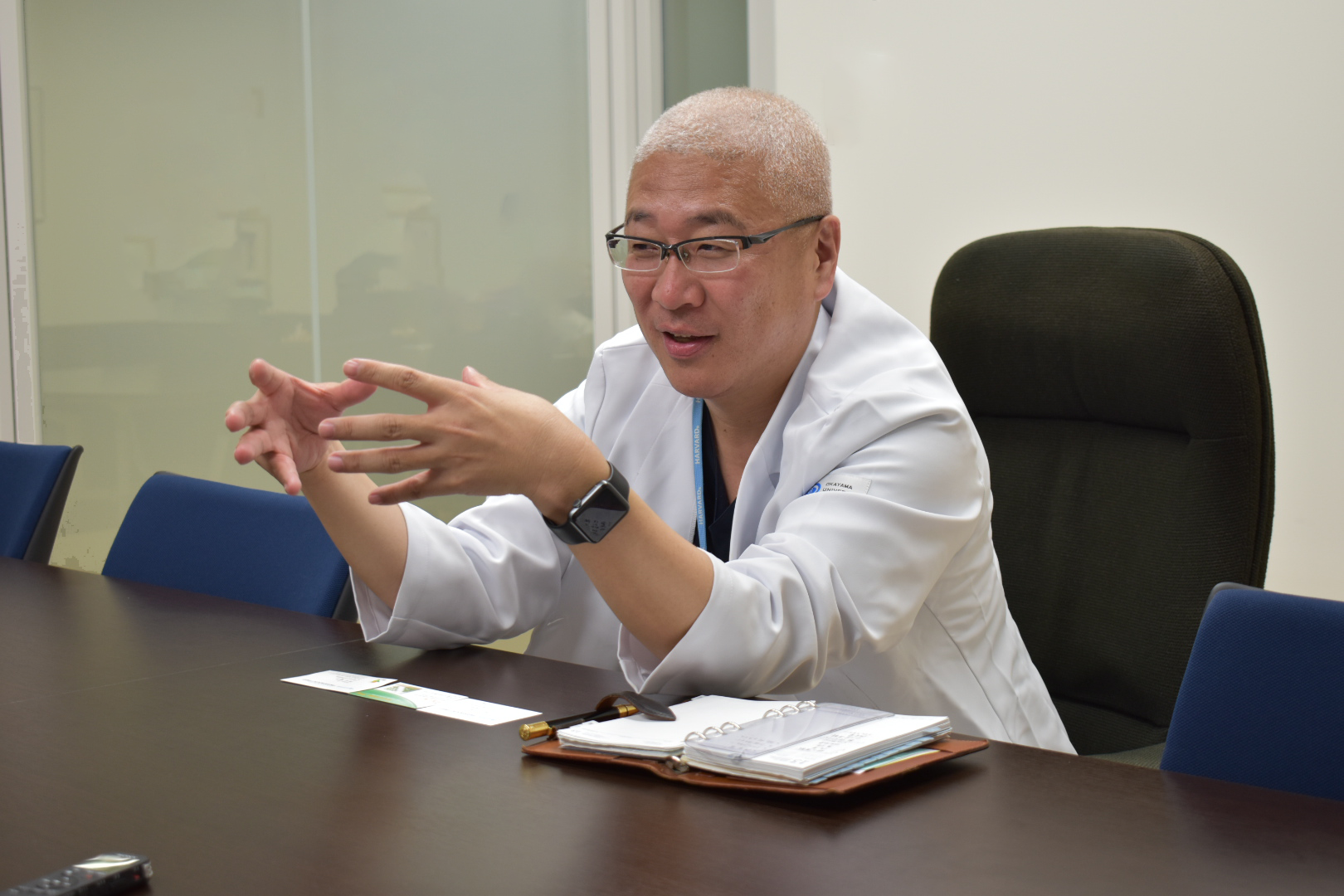
「光」や「音」からICUの設備環境を見直してみよう
――ICUの環境を改善するといっても、何から手を着ければいいのでしょうか。森松先生が考えるポイントを教えてください。
私がICUの環境に関して気になることの一つが「不自然な光」です。ICUでは、処置やケア、それらの準備などの都合もあり、夜間であっても自宅のように暗くすることは難しいのが現実です。医療従事者も努力してはいますが、どうしても消せない照明もあって、患者さんが心地よく眠れる環境とは言いづらいでしょう。当院でも心がけていることですが、「昼は明るく、夜は暗く」が基本的なあり方だとあらためて認識したいですね。真っ暗にすることができないにしても、せめて患者さんの目に入る光量を減らすよう、照明の位置や色味などの調整、あるいは効果的なカーテンの活用方法などを検討できるといいですね。それと同時に、壁や天井の色、図柄などに配慮することも有効でしょう。こうした点については、より胎内に近い環境を演出するなど環境整備に対する意識や技術が高いNICUの知見を応用できるかもしれません。さらに今後は、VR(仮想現実)やプロジェクションマッピングなど最新技術の力を借りて、患者さんに提供できる環境の可能性を広げていくという方向性もあるかもしれませんね。
より根本的な改善案としては、窓の設置も考えられます。自然光や、それによる影、そして光と影で作り出される立体感をもたらしてくれる窓により、ICUに生じがちな圧迫感を軽減できるはずです。日中に少しでも太陽の光を感じることで、睡眠の質を改善させることにも一役買ってくれるでしょう。人工の照明をうまく調整することに加え、このように自然の力を借りることも大切だと思います。これからの時代のICUは、こうした点まで考慮して設計するのが当たり前になっていくかもしれません。
――「光」のほかにも、患者さんに大きな影響を与える環境要因はありますか。
例えば、「音」はどうでしょう。耳障りなアラーム音が始終鳴り響いているというのは、患者さんにとって想像を超えるほどのストレスになり得ます。医療従事者にとっては当たり前の環境ですが、音量や機器の位置などを含めて現状が本当にベストなのか、あらためて検討してみるべきだと思います。
また、患者さんに非常に多くのラインがつながれているというのも、ICUにありがちな光景です。輸液はもちろんのこと、人工呼吸器、体温や血圧、心電図、脳波などのモニター、膀胱留置カテーテルなど、平均して10本程度はあるはずです。重症度の高い患者さんでは20本を超えるケースもあり、「ベッドサイドに足の踏み場もない」といった状況もあり得るのではないでしょうか。これだけ多くのラインにつながれていては、患者さんもストレスを感じて当然です。せん妄などがあって自己抜去してしまう患者さんを薬剤で鎮静させようとすると、今度は昼夜逆転につながることもあります。ラインをゼロにはできないとしても、最低限に抑える必要はあるでしょう。いずれはメーカー側の協力も得て、ラインやケーブルを整理しやすいよう規格を統一していくことも大切だと思います。

エビデンスを待つよりも「試してみる」勇気を持とう
――生活リズムを整えるためには、日中にしっかり覚醒し、可能な範囲でリハビリテーションに取り組むことも重要だそうですね。
寝たきりの状態ができるだけ短くなるよう、ICUでも早期離床を促すのが近年の流れです。座位を取ることで筋力低下を予防し、日中の活動量を高めることにつながるため、座ることは大切なテーマの一つです。
ところが、安全性を最優先するICUのベッドは、大きく、重く、動かしにくいものが多い。そういうベッドは幅が広いため、筋力の衰えた患者さんが腰かけたときに体幹を支えにくいですね。また、リハビリテーションのためにわざわざ専用の車椅子やベッドに移乗・移動させる病院も多く、決して患者さんが離床しやすい環境とはいえません。ベッドそのものの改善とともに、ICUでも使いやすい座り心地の良い椅子が誕生することを期待しています。
日中の覚醒度を高めるという観点では、リハビリテーション以外のサポートを考えることもできるでしょう。多くのICUには、生活の中で楽しみになるような要素がほとんどありません。一般の病室のようにテレビを置いたり、インターネット環境を整えたりするといった簡単なことでも、日中の覚醒度を高めることにつながるはずです。「もし、自分がICUに入院したら……」と想像すると、オンデマンドの動画配信サービスで映画を観たり、音楽を聴いたりできたらうれしいですよね。「○時以降は禁止です」といったルールを設ければ、より普段の生活に近いリズムもつかみやすいでしょうし。
――ICUというと、家族の面会にも大きく制限されるイメージですが、その点についてはどうお考えですか。
20年以上にわたり集中治療の現場に立っている私が感じてきたのは、生命の危機に瀕しているときこそ、本人の「何としても生き続けたい」という意欲が極めて重要だということ。「もういいや」とあきらめの気持ちになってしまったら、なかなか元気になるのは難しい。患者さん自身が強い気持ちを持って治療に臨むためには、モチベーションが必要不可欠なのです。それを考えるとき、とても大きな要素となるのは家族の存在でしょう。「また家族と一緒に過ごしたい」「元気になって家庭を守らなくては」という気持ちが、患者さんの回復に与える影響は計り知れません。
ところが、現在のICUは家族が面会に来るための制限がかなり多い。そのハードルを越えてベッドサイドを訪れても、ICUの環境は家族にとって居心地が悪いことも多いのです。椅子もなく立ちっぱなし、騒がしい状況の中で、わずかの時間だけ顔を合わせても、落ち着いてコミュニケーションすることは難しい。感染予防という視点も忘れてはなりませんが、もう少し気軽に家族と話せるような場を提供することも必要ではないでしょうか。例えば、当院では症例や容態によっては面会フリーとしているほか、ICUの一角をフリースペースとして面会に活用してもらっています。
――最後に、ICUで働く医療従事者や、ICUの環境作りに携わる人たちへメッセージをお願いします。
医療従事者を中心にデザインされた現在のICUは、患者さんの生活という観点からは必ずしも心地良い環境ではありません。もちろん、集中治療の現場として安全性を担保することは重要です。しかし、それだけを追求していくと、「実は患者さんの心身に悪影響を及ぼしていること」に無頓着になりかねません。医療現場に普及してきた「ペイシェント・センタード」という概念は、今後はICUにも適用されていくべきでしょう。
ここで注意したいのが、悪い意味でエビデンスにこだわりすぎないことです。ICUにおける取り組みについては、比較対象となるグループを用意して明確に影響を評価するのが難しいことも多いのですが、「エビデンスが明確でないことは不要」という考え方では、何も変えないことがベストになってしまいがちです。
しかし、目の前の患者さんが少しでも適切な状況に置かれるよう、創意工夫を重ねるのが医療従事者の本懐であるはずなのです。まずは一定の指標をもとに、単純に取り組みの導入前後を比べるだけでも十分だと思います。たとえ根拠となる論文がないとしても、経験則として皆が「いい!」と思ったものは自然に広がっていくのではないでしょうか。
患者さんにとって「異常な環境」であるICUが、現状のままでいいとは思えません。まずは、その問題意識を持つことです。そして、患者さんの立場から考え、固定観念に縛られずに「普通の環境」へ寄せていこうとする姿勢こそ、これからの集中治療に携わる人間に求められることではないでしょうか。